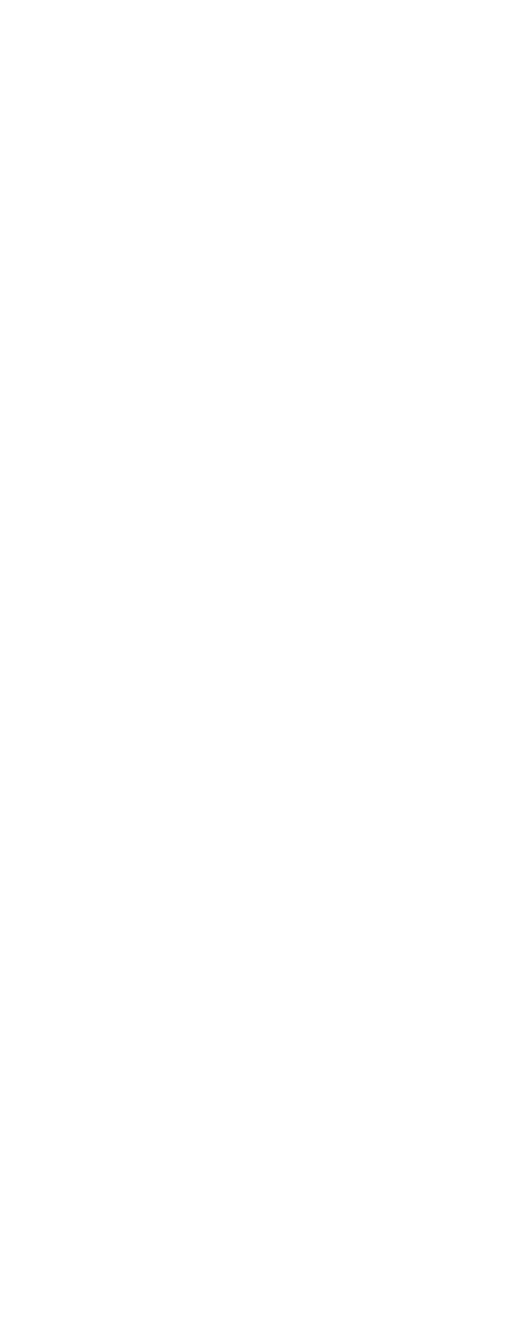
不動寺は、平安時代に弘法大師によって 開かれた由緒あるお寺です。 大阪市の古地図には、北区曽根崎兎我野町に その名が記されていますが、 現在の地である豊中に移転してから、 約60年の歳月が経ちました。 ぜひ一度、足を運んで その歴史と境内の美しさを直接ご覧くださいませ。
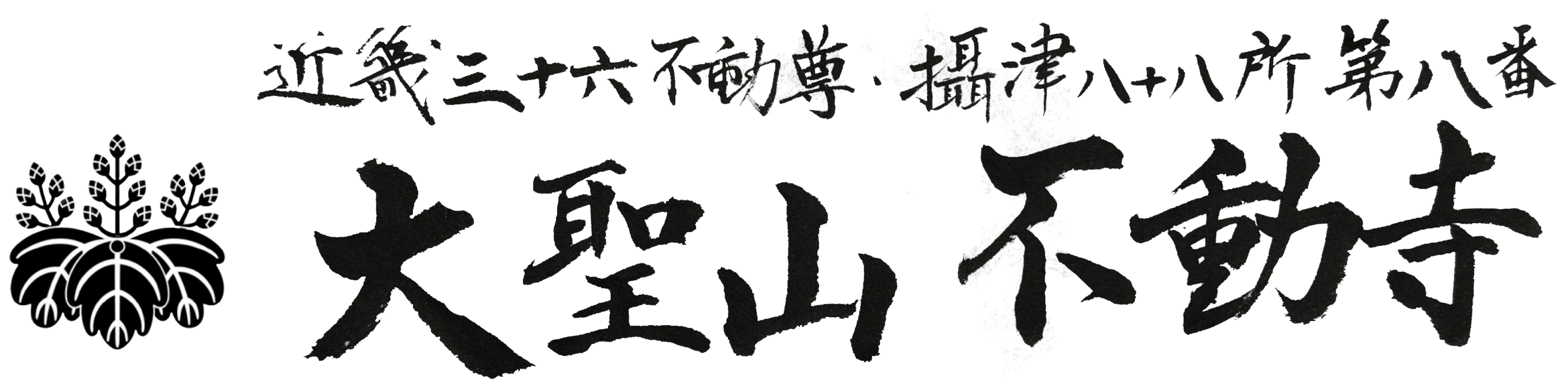
ブログ

令和7年9月21日(日)14時~ 大聖山不動寺 秋季彼岸会法要のお知らせ

令和7年 秋季彼岸会法要のお知らせ
大聖山不動寺【2025年 秋のお彼岸】
秋分の日を中日とした一週間は「秋のお彼岸」です。
お彼岸とは、迷いの世界「此岸(しがん)」と悟りの世界「彼岸」を分ける川を渡り、心安らかな彼岸に到達することを願う、仏教に由来する大切な行事です。
この期間には、ご先祖さまや亡き方々を思い、感謝の気持ちと祈りを捧げることで、日常の慌ただしさから離れ、心を整える時間を持つことができます。
大聖山不動寺では、皆さまが安心して心静かに過ごせるよう、毎年秋季彼岸会法要を執り行っています。
初めてご参列される方も安心してご参加いただけるよう、法要の流れや供養の方法についても丁寧にご案内いたします。
法要日時・会場
- 日時:令和7年9月21日(日)14:00~
- 会場:大聖山不動寺
豊中市宮山町4-7-2 - お問い合わせ:TEL 06-6855-0079
法要は読経とともに、施餓鬼供養、塔婆供養、お供米の奉納などを行います。
ご家族でのご参列はもちろん、お一人でも安心してご参加いただけます。
施餓鬼会とは
施餓鬼会(せがきえ)とは、亡き方々やご先祖さま、さらには迷える霊に対して食べ物や供養を施すことで、功徳を積む仏教行事です。
- 餓鬼に食べ物や飲み物を供えることで、亡き方々の成仏を祈ります。
- 施餓鬼は、私たち自身の心を清める修行の意味もあります。
- 法要を通じて、故人やご先祖さまへの感謝の気持ちを新たにできます。
塔婆供養・お供米について
秋季彼岸会では、以下のご供養を承っております。
種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
塔婆供養料 | 3,000円/1霊 | 塔婆1本につき1霊のご供養です。故人やご先祖さまのお名前を記し、法要中に丁寧に供養いたします。 |
お供米料 | 1,000円 | ご先祖さまへのお供えとして、心を込めて捧げます。 |
申し込み方法
- 申し込み用紙は別封筒にてご記入ください。
- 当日は混雑が予想されますので、郵送またはゆうちょ銀行振替用紙による事前受付にご協力ください。
事前振込について(ゆうちょ銀行)
ゆうちょ銀行
- 店番:418
- 種別:普通
- 口座番号:9732775
- 名義:タイセイザンフドウジ
※インターネットバンキングでお振込みの場合、当方にはカタカナ名のみが表示されます。
振込内容(施餓鬼料・塔婆供養料・お供米料の内訳、霊名など)は、FAX・LINE・電話いずれかで必ずご連絡ください。
法要の流れ(例)
- 受付(事前申し込みの方はスムーズに)
- 法要開始(読経・焼香・施餓鬼)
- 塔婆供養の奉納
- お供米の奉納
- 法要終了後、参加者のご参列・ご焼香
※所要時間は約1時間程度です。
参列時の服装・持ち物
- 服装:略礼装で問題ありません。季節は秋ですので、羽織物など体温調整しやすい服装がおすすめです。
- 持ち物:申し込み用紙(事前提出済みの場合は不要)、お供え(塔婆・お供米希望の方は受付でも可能)
- 心構え:法要中は静かに手を合わせ、心を込めてご先祖さまへの感謝を捧げましょう。写真撮影や携帯電話の使用は控え、法要の雰囲気を尊重してください。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 初めて参加しても大丈夫ですか?
A. はい、初めての方でも安心してご参加いただけます。スタッフが丁寧にご案内いたします。
Q2. 塔婆は何本まで申し込めますか?
A. 塔婆1本につき1霊です。複数霊を供養される場合は本数分お申し込みください。
Q3. 服装はどのようなものが良いですか?
A. 略礼装で大丈夫です。お子さま連れでも安心してご参列いただけます。
Q4. 当日、受付だけで申し込みはできますか?
A. 可能ですが、当日は混雑が予想されます。事前申し込み・事前振込をおすすめします。
皆さまへのお願い
- 当日は多くの方が参列されます。事前受付・振込にご協力いただくと、スムーズに法要を執り行うことができます。
- 塔婆1本につき1霊です。複数霊の供養は本数分お申し込みください。
- 法要参加に不安のある方も、遠慮なくお問い合わせください。
💡 まとめ
- 秋のお彼岸は、心穏やかにご先祖さまへの感謝を捧げる大切な期間です。
- 大聖山不動寺では、施餓鬼・塔婆供養・お供米など、多彩な供養が可能です。
- 事前の申し込み・振込により、当日の混雑を避け、安心して法要に参加いただけます。
- ご家族・ご友人と共に、心静かにご先祖さまを偲ぶひとときをお過ごしください。







